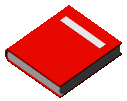 調べる  調べる 聞く 見る 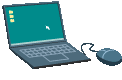 |
★意外と知られていないのではないでしょうか?★ 「差額ベットはどの程度か?」「看護師の数は十分なのか?」 病院で治療を受けたあり、入院する時、知りたい事はあっても 中々正確な情報は得られないと思いがちです。 ところが病院内には費用などについて重要な情報が掲示されているので 注意深くチェックして欲しい。 差額のベッド代 例えば、「305号室(個室)12、600円、(4人部屋3、675円)・・・」 東京都杉並区にある救世軍ブース記念病院には入院費の支払い窓口のカウンターに 一日あたりの室料(差額バッド代)の一覧表が張ってある。 個室などを希望する入院患者はこの表を見れば、通常の医療費の他にベッド代が どの程度かかるかが分かる。 一日12600円の個室に入っている80才代のS男さん。7月の請求額が31日分 だから390、600円と、単純明快だ。 差額ベッド代は患者一人当たりの面積が6.4平方メートル以上である事などの 条件を満たせば、病院が自由に料金を設定して徴収できる。 4人部屋でも徴収可能だが、原則として全入院ベッドの半分までしか設定できない。 病院が「差額のベッド代の部屋しか空いていない」と、一方敵に患者を入院させる事は 認められない。 患者にきちんと説明して同意を得る事が必要だ。 病院は各部屋の料金を役所に届け出て、病院内に掲示することも義務づけられているので、 患者によって料金を変えるようなことも出来ない。 規則通りに料金が掲示されているかどうかを確認したい。 紙おむつ代 救世軍ブース記念病院の窓口にはもう一つ重要な表示がある。 「紙おむつ1枚180円、尿取りパット1枚120円」などとされた料金表だ。 同病院は慢性病などの高齢者が長期間入院できる「療養病床」が中心の病院。 いわゆる老人病院だ。 この種の病院ではおむつ代やパジャマ代、各種サービスなどを含めた料金として中身が あいまいな費用を徴収することがある。 「お世話代」「雑費」などと称することもあるようだ。 実はこのような形の費用徴収は認められていない。 厚生労働省はこの病院の料金表のように、個々の「サービス」や「モノ」について料金を明示して 院内に掲示する事を求めている。 個々の料金がはっきりしていれば、最終的な請求額も納得しやすい。 先ほどのS男さんの場合は「おむつ代」で24、480円。月に136枚使った計算だ。 このような費用や差額ベッド代には健康保険などの公的医療保険は適用されない。 70才以上の患者は保険証を使えば、治療代や入院費などの部分はかかった費用の原則一割だけ 負担する仕組み。この一割負担には月40、200円の上限(低・高所得者は別)も定められている。 S男さんの7月の一割負担は上限を超えたので、実際の請求額は40、200円だ。 このほか一食260円と決まっている食費が24、180円。 おむつ代と差額ベッド代を合わせて7月の総請求額は479、460円。 中身は明解なので「請求額についてのクレームはほとんどない」(同病院の徳永貴士・医事課長) という。各種診断書、証明書なども料金の表示義務づけられている。 千葉市のある中規模病院の死亡診断書の料金は一通当たり3、150円。 東京都内ではこれよりも高いところもあれば、地方ではさらに安い料金もあるという。 様々な費用を徴収される前に、院内掲示情報をよく見ておくことが大切だ。 入院基本料 「当病棟で1日に勤務している看護師の数は以下の通りです。日中(朝8時〜夕4時)7〜9人、 夕方(4時〜深夜零時)3〜4人、深夜(零時〜8時)3〜4人」 東京都中央区にある聖路加 国際病院の入院病棟にはこんな紙が張り出してある。 一病棟の入院ベッドは35。稼働率を考慮して入院患者は32人程度だとすると、昼間は 看護師一人でおよそ4人の患者を、夜は10人前後の患者をみていることになる。 厚生労働省はこの4月(2006年)から患者にわかりやすい情報提供の一環としてこのような 看護職員の配置状況の掲示を義務づけた。  各時間帯によって「看護職員一人当たりの受け持ち患者はxx人以下です」と掲示する 病院も多い。一般的に看護師の人数が多いほど手厚い看護が出来る。 聖路加病院は最も手厚い部類に入る。 実際に看護師の配置の厚さで病院を選ぶ患者はいないかもしれないが、手厚いほど医療費も 高くなる仕組みになっている事は頭の片隅に入れておいてもいいかもしれない。 最も手厚い配置の病院が得る入院基本料は患者一人一日につき15、550円。 最低基準の配置の病院だと9、540円。 患者はこの1〜3割を負担するので、入院基本料が増えればその分だけ患者負担も増す事になる。 患者本位の意識薄く「病院任せ」と国への不満も 病院内での情報の掲示については、本当に患者にとって分かりやすいものになっているのか 疑問も多い。国が義務づけているから仕方なく掲示しているという例が珍しくなく、掲示場所も言葉も 分かりにくかったり、掲示すらしていなかったりする例もある。 各地の社会保険事務局が病院を調べ、掲示していない場合は指導したり、悪質なら保険診療の 停止などの処分を下したりする。 ただ頻繁にしらべることもできないので、更新されていない古い情報が掲示されていることも あるようだ。 病院側にも言い分はある。医療費は抑えられ病院の収入は伸びない。 そんな中で情報提供に力を入れる余力はなくなってきているという。 10月(2006年)から制度改革で高齢者を中心に医療費負担がまた増える。 そのような負担増を現場で患者に説明するのは医療機関任せで、「制度変更を決めた国は何も してくれない」との不満も渦巻いている。 患者が効率的によりよい医療を受けるため、情報開示の一層の充実が必要。 インターネットなどを通した病院情報もあふれつつあるが、中身は玉石混交だ。 形だけの開示ではなく、患者にとって本当に役立つ情報開示とはどんなものか、改めて 検討する余地はありそうだ。 (日本経済新聞2006年9月10日から抜粋) 公私・病院・施設 リンク集 |